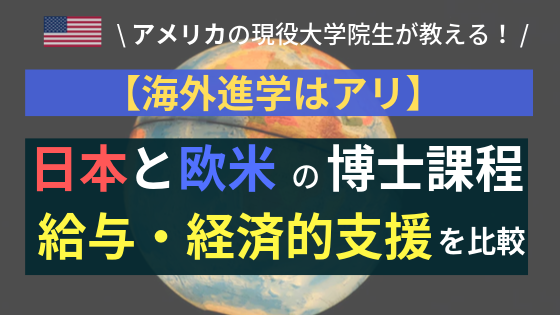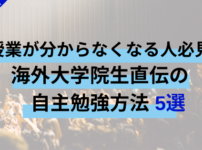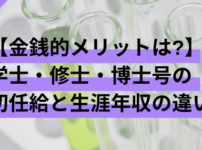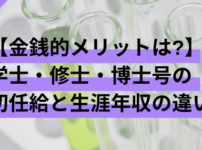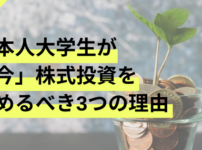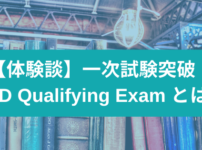みなさん、こんにちは。
このブログを運営している理系しまびとです。
この記事では、博士課程の給与を国別で調べた結果をお伝えします。

こんな方におすすめ
- 理系で博士課程に進む予定・迷っている方
- 海外大学院への進学に興味がある方
この記事を読めば、
海外と日本の博士課程の経済的待遇や給与の目安がわかります。
また、海外大学院へ進学するメリットの一つである給与について理解することができます。
この記事では、欧米のPhD Studentと呼ばれる学生の給与について解説します。
日本とは大学院のシステムの違いがありますが、日本の博士課程後期の学生と海外のPhD Studentが同等として書いています。
海外大学院や博士課程へ進学を考えている方の参考になれば幸いです。
システムの違いや海外大学院の博士課程についてはこちらの記事を参考にご覧ください。
-
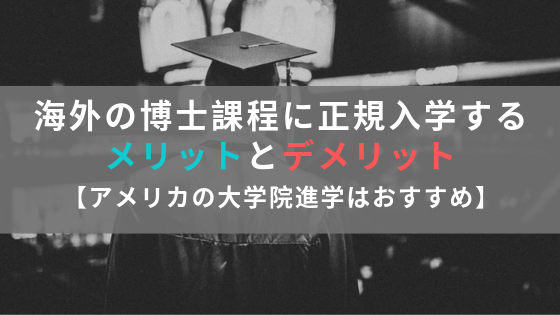
-
理系が海外の博士課程に正規留学するメリットとデメリット【アメリカはおすすめ】
こんにちは、このブログを運営している理系しまびとです。 僕はアメリカ・ニューヨークの大学院のDoctoralコースに在籍しているPhD Studentです。 別の言い方をすると、海外大学院に正規留学中 ...
続きを見る
もくじ
日本と欧米の博士課程の給与・経済的支援を比較
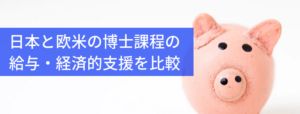
まず始めに、日本の博士課程は基本的に給与はありません。
ほとんどの場合、欧米の海外大学院の博士課程(PhDプログラム)であれば、授業免除と基本的に教授から生活費に充てられる給与がもらえます。
給与がもらえることは海外大学院へ進学するメリットの一つであり、実際に僕がアメリカで博士課程に進学した理由の一つです。
僕はアメリカの海外大学院に在籍しているのですが、国によって給与に違いがあることに気づきました。
その違いは、国ごとに大まかに決まっていて税金によって手取りの額が違ったりします。
大学によっても給与に差はありますが、基本的に月20~25万円程度でおおよそ同程度です。高くて40万円という感じです。
この額にTAの給与が加算される場合もあります。
しかし、この額は都市か田舎に関係ないように思います。
このように、住む場所の物価や手取りの額によって博士課程に在籍する間の生活はかなり変わってきます。
結論から申し上げますと、
国として物価の高いスイスと北欧諸国は給与が高いです。
また、完全に比較することは難しいですがアメリカよりもヨーロッパの方が若干給与額は高い傾向にあるようです。
物価の違いもありますが、特にスイスの博士課程の学生の給与は高いです。
それに比べて、日本の博士課程の学生の経済的支援はかなり少ないです。
以下に詳しく説明していきます。
日本の博士課程の経済状況
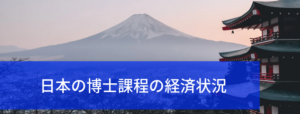
まず、日本では、教授が博士課程の学生に対して給与を支払う制度はまずありません。
奨学金や大学院によって、学生に経済的な支援を行っているケースはあります。
ここでは、有名な日本学術振興会のDC1とDC2について、一般的な日本の博士課程の学生について、公式HPと文部科学省の資料に基づいて説明します。
日本学術振興会のDC1やDC2
日本学術振興会のDC1やDC2は研究奨励金として、月20万円支給されます。
月20万円といっても、所得税や社会保険料、年金、住民税によって差し引かれます。
在学中に年金を支払うかどうかや、税も市町村によって違う場合もあるので一概に言えませんが、前述したものをすべて支払うと手取りは16~17万円ほどになってしまいます。
さらに、①他の奨学金との重複は不可、②学外のアルバイト不可、③受給額の3割は研究遂行経費として使用しなければ追徴課税が行われます。
研究遂行経費としての支出が当該年度の研究奨励金額の3割未満であった場合は、研究奨励金(1年度分合計額)の3割相当額と研究遂行経費の支出報告額の差額に対して、追徴課税を行います。
日本学術振興会公式HPより引用(2019年10月1日)
博士課程の学生が経済的な支援を受ける上で、DC1とDC2は最も待遇の良い制度の一つですが、採択率は約20%で進学する全員が受給できるものではありません。
合格ラインも、ある程度研究実績を残した優秀な方が審査を通過しています。
一般的な日本の博士課程の学生
DC1やDC2を受給していない場合は、経済的に厳しい状況になっている方が多いようです。
経済的な支援まで行う制度は限られていて、その額受給額もDC1やDC2より低い場合がほとんどです。
例えば、経済的支援の受給なしが全体の52%、生活費相当額を受給している人は10.4%です。
DC1やDC2を受給している人はこの10.4%に含まれていると思いますが、一般的な博士課程の学生は受給なしの方が多数派です。
貸与型奨学金を除く、経済的支援の受給総額については、「受給なし」が 52.2%で最も多く、次いで「60 万円未満」が 24.9%、「60 万円以上、120 万円未満」が 7.5%となっており、生活費相当額(180万円)を受給している者は、10.4%である。
「博士課程学生の経済的支援状況に係る調査研究」より引用(2019年10月1日)
さらに大学院なので授業料も発生しますが、日本の博士課程において学費免除を受けている学生は全体で2~3割程度です。
授業料減免措置については、「減免措置を受けていた」が 23.9%、「減免措置を受けていなかった」が 63.5%であり、受けていない者の方が多い。
「博士課程学生の経済的支援状況に係る調査研究」より引用(2019年10月1日)
日本の博士課程
・DC1やDC2を取っても手取りは月17万円程度(重複受給・アルバイトは不可)
・一般的な博士課程の学生の半分以上が経済的受給なし
・生活費相当の経済的な支援を受けているのは約1割
・授業料減免措置を受けているのは約2割
欧米の博士課程の給与体系
欧米の博士課程(PhDプログラム)では、基本的に教授から給与が支払われます。
その代わり、TAとして授業を手伝ったり、学部や修士の学生の研究の補助を頼まれることがあります。

後のセクションで詳しく説明しますが、欧米では手取りが月20万円以上もらえる場合がほとんどのようです。
国や大学によって制度が異なるため、一概には言えませんが、基本的に①授業免除込み、②保険料込み、③場合によっては他の奨学金の受給可能です。
アメリカの博士課程の給与額

例として、アメリカの大学院に通う僕の場合は、年額約300万円(月27万円ほど)から税が引かれた額が手取りとなり、授業免除、保険料込み、奨学金の複数受給可能です。
世界の求人サイトであるGlassDoorのデータでは、アメリカのPhDの給与の平均は$30,604で、給与額の平均は日本円にして月27~28万円程度です。(1ドル110円換算)
そこからFederal Taxなどが引かれて、概算で15~20%差し引かれるとすると、だいたい手取りは20~23万円程度になると思います。
僕の受給額も同じくらいですね。
アメリカの博士課程
・給与の手取りは月20~23万円程度かそれ以上
・基本的に授業免除、保険料の経済的な支援あり
・他の奨学金との重複受給も可能性あり
【ランキング】欧州の博士課程の学生の給与額

続いて、ヨーロッパ圏について調べてみました。
こちらもアメリカと同様に授業料免除や健康保険がカバーされるケースが多いようです。
僕が調べた結果のPhDの給与額の上位3か国のランキングは以下の通りです。
調べた方法は、GlassDoorで実際に募集されているサイエンス系のPhDのポジションを2~3個ほどランダムに調べました。
FASTEPO.comというPhDの給与平均を公開しているサイトとも大きな差はありませんでしたので、ある程度の目安になる信頼性はあると思います。
1位:スイス(約54万円)
ベルン大学、チューリッヒ大学のPhDポジション参考(1ユーロ130円換算)
2位:ノルウェー(約50万円)
ノルウェー科学技術大学のPhDポジション参考
3位:デンマーク(約33万円)
コペンハーゲン大学、南デンマーク大学のPhDポジション参考
物価が高いスイスに高く、次に北欧のノルウェーやデンマークが続きます。
ノルウェーは物価が高い国として知られており税率も高いためだと考えられます。
税が30%取られると考えても、月30万円は超えるので、物価指数から考えても生活費相当以上に値すると思います。
ちなみに、手取りは英語で「Net」と書かれてるので、自分で調べる際は参考にしてみてください。
オランダ、ドイツ、フィンランド、オーストリア、イギリスなどが続き、これらの国に大きな差はなく、EU圏は基本的に手取り月23~25万円程度が多いです。
僕の調べた感覚とドイツで暮らしていた経験からすると、アメリカよりヨーロッパの方が生活費に対する給与額は若干高いか同程度だと思います。
国というより、住んでいる地域によって手元にのこる金額が変わってくる感じですね。
ドイツでいうと、ベルリンやミュンヘンに住むと結構キツイかもしれません。
大きな都市に住まずに、シェアハウスに住んだり、大学の寮などに入ることができたりすれば、かなり生活に余裕があると思います。
欧州の博士課程
・給与は物価に左右され、スイスとノルウェーはかなり高い
・ヨーロッパ圏では給与の手取りは月23~25万円程度が多い(生活費相当以上)
・基本的に授業免除、保険料の経済的な支援あり
まとめ
日本の博士課程の経済的な支援を受けるのは、欧米諸国と比べてかなり困難であるといえると思います。
どこに住むかによりますが、日本の物価を考えれば、月20万円でも欧米と比較して低いと思います。
仮に支援を受けたとしても生活費相当の受給額を受けている学生は1割程度とかなり低いです。
それに比べて、海外大学院の博士課程では、TAとしての業務が含まれている場合がありますが、生活費相当の給与が与えられます。
さらに、基本的に授業料免除や保険料込みであったり、奨学金の受給も許可されている場合があります。
また、アメリカはヨーロッパ諸国と比べて給与は若干低い傾向にあるようですが、生活費によるので生活に余裕があるかは住む場所で決まります。
都市部に住むかどうかで生活費は大きく変わってくるので、給与額だけでなく住む場所も考慮するといいと思います。
海外大学院の博士課程へ進学メリットの一つとして、給与がもらえることが挙げられますが、経済的な支援を考えると「海外進学はアリ」だと思います。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました。
関連記事
こちらの記事では、海外大学院の博士課程の給与のパターンについて詳しく説明しています。
実は、僕は給与としてではなくフェローシップとして受給していて、TAの義務はありません。
気になる方は合わせてご覧頂ければ、さらに理解が増すと思います。
-
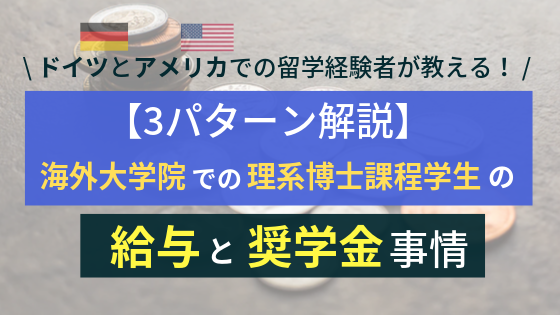
-
【3パターン解説】海外大学院での理系博士課程学生の給与と奨学金事情
みなさん、こんにちは。 このブログを運営している理系しまびとです。 この記事では、 アメリカの海外大学院の博士課程(PhD)に進学した僕の年収(給与)や給付型の奨学金についてお伝えします ...
続きを見る
\ 為になったと思ったら /
\ 友達にシェア・ブックマーク /